毎年9月は食生活改善普及運動月間です最終更新日:2025年08月29日
生活習慣病の予防、健康的な生活を送るためには、適切な量と質の食事をとることが大切です。まずは自分の食生活を見直し、「まずは毎日、あと一皿ずつ野菜と果物をプラス」をテーマとして、次の重点項目を参考に、できることから健康づくりを始めてみましょう。
重点項目①「野菜はプラス1皿(100g)食べましょう」
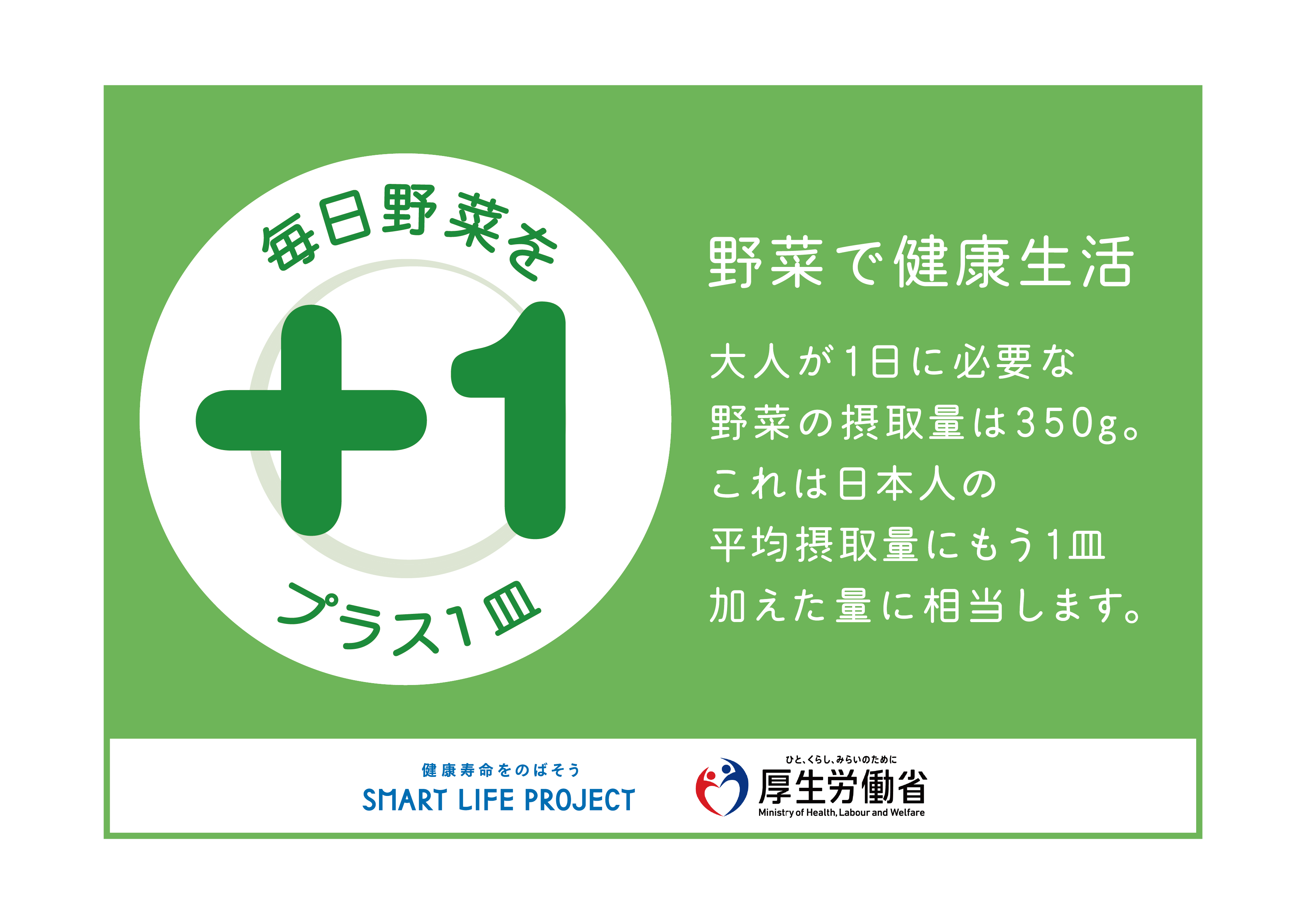 野菜は1日350g食べることが推奨されています。
野菜は1日350g食べることが推奨されています。日本人の平均野菜摂取量は256g(令和5年国民健康・栄養調査)であり、あと100gの増加が必要です。
野菜100gは小鉢約1皿分に相当するため、今の食事にプラス1皿野菜料理を追加しましょう。
町民向けに実施した令和4年度健康意識調査では、毎食野菜を食べる方の割合が、全体の35.3%でした。
野菜料理や具沢山の味噌汁など、意識して食事に取り入れてみましょう。
おすすめレシピ→長いものポテトサラダ風
【健康やはば21(第3次)目標】
毎食野菜を食べる方の割合の増加
| 現状値(R4年度) | 目標値(R15年度) |
| 35.3% | 45.0% |
重点項目②「果物はプラス1皿(100g)食べましょう」
 令和5年度国民健康・栄養調査の結果では、果物の摂取量は男性で0gの方が45.5%、女性で0gの方が35.3%と最も多かったです。
令和5年度国民健康・栄養調査の結果では、果物の摂取量は男性で0gの方が45.5%、女性で0gの方が35.3%と最も多かったです。果物は1日200g食べることが推奨されています。
果物にはビタミン、ミネラルが含まれており、体の調子を整えてくれます。
複数回に分けて食べると、必要な量を無理なく食べることができます。
例)100gの果物…キウイフルーツ1個、みかん1個
おすすめレシピ→ヨーグルトゼリー
重点項目③「バランスの良い食事をとる」
 主食・主菜・副菜をそろえた食事を意識しましょう。
主食・主菜・副菜をそろえた食事を意識しましょう。主食・主菜・副菜をそろえた食事を1日2回とっている場合、それ以下の場合と比較して、栄養素摂取量が適正となることが報告されています。
バランスの良い栄養を摂ることは生活習慣病予防につながることから、若い頃から主食・主菜・副菜がそろった食事をとる習慣をつけることが大切です。
【健康やはば21(第3次)目標】
主食・主菜・副菜をそろえた食事が1日2回以上の日がほぼ毎日の方の割合の増加
| 現状値(R4年度) | 目標値(R15年度) | |
| 20歳代 | 30.2% | 40.0% |
| 30歳代 | 44.0% | 55.0% |
| 40歳代 | 46.8% | 57.0% |
重点項目④「食塩は控えめに。うす味を心がけて。」
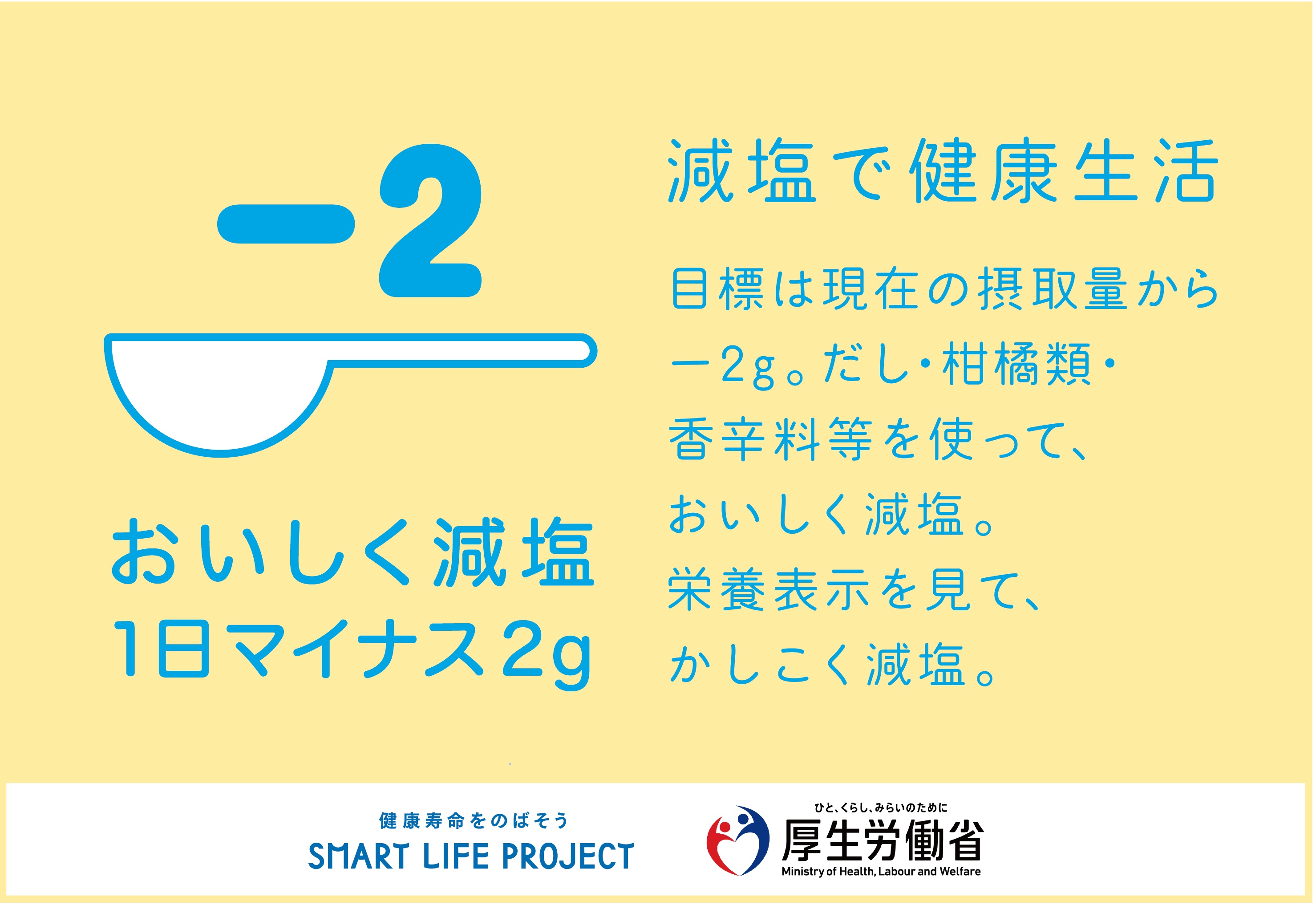 矢巾町の食塩摂取量は男性9.2g、女性8.7g(健康やはば21(第3次))と、目標量よりも約2g多い状況です。
矢巾町の食塩摂取量は男性9.2g、女性8.7g(健康やはば21(第3次))と、目標量よりも約2g多い状況です。町内園児、小中学生、保護者向けに実施した食育アンケート調査では、加工品(ウインナー、ハムなど)を食べる頻度が4~5日以上の方が全体の33.8%と約3人に1人という結果でした。
ウインナーやハムなどの加工品には食塩が多く含まれているため、食べる頻度を減らすことによって減塩につながります。
たんぱく質は肉や魚、卵、大豆製品などからとるように心がけましょう。
【健康やはば21(第3次)目標】
塩分摂取量の減少
| 現状値(R4年度) | 目標値(R15年度) | |
| 男性 | 9.2g | 7.0g |
| 女性 | 8.7g | 6.5g |
健康やはば21(第3次)
ポスター
このページに関するお問い合わせ
健康長寿課 成人健康係 (電話:019-611-2822)
健康・福祉
毎年9月は食生活改善普及運動月間です
紫波郡の休日救急当番医日程表
フレイル測定会を開催します
出前講座「筋力アップでいきいき元気!」が開催されます
公用車(リース車両)1台の車検切れについて
令和7年度 おやこの食育教室を開催します!
さわやかハウスの利用について
資格確認書、医療費受給者証の更新について
障がい者医療費助成制度
やはば健康チャレンジ事業「健康ポイント」について
熱中症を予防しましょう!
お亡くなりになられた方の介護保険料及び介護給付費に関する手続きについて
矢巾町介護認定審査会について
百日咳の感染が流行しています
シルバーリハビリ体操指導者養成講習会の受講者募集!
令和6年12月2日から国民健康保険及び後期高齢者医療の保険証が廃止になります
後期高齢者医療における資格確認書の交付延長について
無料低額診療事業における調剤処方費の助成について
【事業者向け】介護予防・日常生活支援総合事業単位数サービスコードについて
【申込終了】令和7年度盛岡地域市民後見人養成講座受講者募集について
「やはば健康チャレンジ」参加者募集中!
令和7年度特定健診等各種成人検診について
矢巾町特定健診受診キャンペーンの開催
【予防接種】帯状疱疹ワクチンの接種について
「特定健診受診キャンペーン」の協賛を募集します
【事業者向け】矢巾町福祉施設等物価高騰対応重点支援金について
第3次矢巾町食育推進計画 概要版を作成しました
認知症について
成年後見制度について
やはば健康チャレンジ事業 データ送信強化月間を開催します!
【介護事業所向け】指定申請等の電子申請・届出システムについて
福祉目線の広報紙「じょいjoy」の紹介
子ども医療費助成についての大切なお知らせ
子ども医療費助成事業
妊産婦医療費助成事業
【予防接種】おたふくかぜワクチンの接種について
【予防接種】乳幼児・児童・生徒の予防接種について
【予防接種】HPVワクチン(子宮頸がんワクチン)の接種について
【令和6年8月から】矢巾町妊産婦医療費助成制度を拡充します
【予防接種】五種混合ワクチンについて
【予防接種】成人男性の風しん抗体検査・予防接種について
【予防接種】高齢者用肺炎球菌ワクチンの接種について
【予防接種】県外での接種を希望される方へ
高齢者等への緊急通報装置の貸し出し
食生活改善推進員養成講座 受講者大募集!
がん患者医療用補整具(医療用ウィッグ・胸部補整具)購入費の助成を行います
町高齢者福祉計画・ 第9 期介護保険事業計画策定について
第2期矢巾町成年後見制度利用促進基本計画
矢巾町国民健康保険 第3期データヘルス計画・第4期特定健康診査等実施計画
健康やはば21(第3次)を策定しました
シルバーリハビリ体操を一緒に行いましょう!
矢巾町高齢者福祉計画・第9期介護保険事業計画の町民説明会の開催について
矢巾町高齢者福祉計画・第9期介護保険事業計画策定のための意見公募(パブリックコメント)について
やはば地域の居場所マップ
【事業者向け】介護予防・日常生活支援総合事業(第1号事業者)の指定更新について
矢巾町高齢者福祉及び介護保険事業計画策定業務委託に係る契約締結について
「矢巾町認知症とともに生きるまちづくり条例」を制定・施行について
【令和5年8月から】医療費助成の現物給付対象拡大について(高校生)
ひとり親家庭医療費助成事業
令和5年度の介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に係る届出について
出産育児一時金の支給
令和5年4月1日から矢巾町骨髄ドナー支援事業を開始します。
【国民健康保険】高額療養費制度について
【国民健康保険】人間ドック受診の助成制度について
マイナンバーカードの健康保険証利用について
【国民健康保険】限度額適用・標準負担額減額認定証について
【国民健康保険】加入・脱退・変更等の手続き
【国民健康保険】新型コロナウイルス感染症傷病手当金の支給について
【国民健康保険】被保険者証について
骨髄移植のドナー登録にご協力ください
【国民健康保険】高額療養費支給申請手続きの簡素化について
【国民健康保険】「医療費についてのお知らせ」(医療費通知)について
介護保険に関する申請書
公費負担医療対象者の高額介護サービス費の算定誤りについて
矢巾町保健師人材育成マニュアル及び矢巾町新任期保健師人材育成マニュアル(第2版)を策定しました
【利用者向け】【事業者向け】介護予防・日常生活支援総合事業のサービス利用について
ポリファーマシー(多剤服用)について
ケアマネジメントに関する基本指針について
【国民健康保険】交通事故や傷害事故(第三者行為)などで病院を受診するとき
介護予防のための「健康教室」開催中!
やさしさはばたく おれんじガイド(矢巾町認知症ケアパス)について
コグニサイズDVDについて
医療費助成給付申請書について
【国民健康保険】保健事業実施計画(データヘルス計画)・特定健康診査等実施計画
矢巾町成年後見制度利用促進基本計画
セルフメディケーションについて
後発医薬品(ジェネリック医薬品)の利用について
矢巾町の介護サービス事業者マップ
矢巾町介護予防・認知症施策推進拠点施設(矢巾町えんじょいセンター)について
「みまもりタグ」購入費用の助成事業について
配食サービス
矢巾町介護予防・認知症施策推進拠点施設「矢巾町えんじょいセンター」を開所しました
保健推進員協議会
【事業者向け】介護予防・日常生活支援総合事業単位数マスタおよびサービスコード表について
介護保険制度の概要
要介護・要支援認定の申請からサービスの利用まで
【事業者向け】介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等について
介護予防・日常生活支援総合事業のお知らせ(事業者向け)
認知症初期集中支援チーム
入院時の食事標準負担額の減額
制度の概要
寝具洗濯乾燥サービス
介護用品支給サービス
在宅要介護家族 介護慰労金(介護手当)
認知症見守りSOSネットワーク
高齢者にやさしい住まいづくり推進事業
高齢者の入所施設のご案内
シルバー人材センターへの仕事依頼
シルバー人材センターへの入会方法
矢巾町老人クラブ連合会
介護サービスを利用できる人
要介護・要支援認定の申請方法について
寡婦医療助成事業
未熟児養育医療制度
